輪講とプレ卒研の進め方
全員参加の輪講はZoomで週1回行います。それ以外にも同じ分野のグループあるいは個別で適宜Zoomによる打ち合わせを行います。毎回、1週間の研究の進捗状況の資料を作成してもらい発表してもらいます。また、他の人の発表を聴いて質疑応答をしてもらいます。
輪講とプレ卒研の主な作業
暫定的にテーマを選んでもらい、関連する卒業論文、修士論文、英語の専門誌の論文を読んでもらい資料にまとめて発表してもらいます。
機械学習の環境を整えるため、パソコンにWSL(Windows Subsystem for Linux), Hyper-V, VirtualBox などの仮想環境上にUbuntu Serverをインストールし、さらにUbuntu上にPythonのプログラミング環境のAnaconda, JupyterLab などをインストールしてもらいます。また卒論はLaTeXを用いて作成してもらうので、LaTeX環境も整備してもらいます。パソコンを持っていない人には研究室のパソコンを貸し出します。
研究室のNVIDIA GPUを装備したUbuntu Server上で動作するJupyterLabに家のパソコンから接続してもらい、時間のかかる深層学習などの計算を実行してもらいます。
木下研に適した学生像
- 進学希望の人、理工系の学生は博士前期課程(修士課程)への進学は必要です。進学することで将来の選択肢が大幅に増えます。特に研究、開発、設計部門などの職種を希望する場合、進学は必須です。生涯賃金にも大きな差が出るので、投資以上のリターンが得られます。
- 積極的に研究活動できる人、情報系の研究室はひとりひとり異なるテーマに取り組みます。自主的かつ計画的に研究をすすめていかないと卒業できません。
- プログラミングが好きな人、主にPythonを用いたプログラミングが必須です。プログラミングが苦手な方にはつらいです。
- 国語と英語の得意な人、研究に必要な文献は、ほぼ英語です。また論理的かつ簡潔な正しい文法の日本語を書くことは理工系にとって必須です。
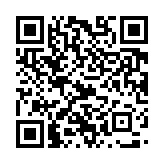
https://k.ee.kanagawa-u.ac.jp/seminar/
問い合わせ kino@kanagawa-u.ac.jp
